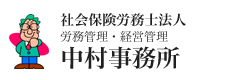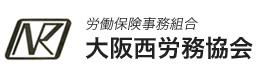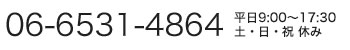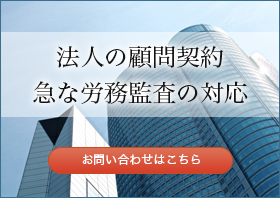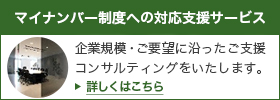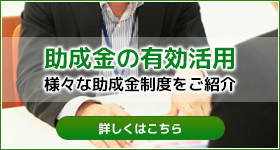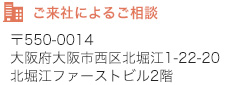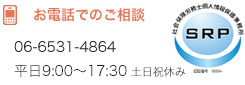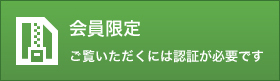テレワークにおける在宅勤務手当・通勤手当の社会保険等・源泉所得税の取り扱い
コロナ禍による感染症対策のため、在宅勤務が急速に拡大する一方で、恒常的にテレワークによる勤務制度を検討する企業が増えています。本格的な導入にあたり、在宅勤務制度に伴う実務上の注意点を確認しておきましょう。
在宅勤務制度に伴う検討事項
2020年4月以降の緊急事態宣言のもと、企業ではテレワーク、なかでも在宅勤務の導入が急速に広まりました。
感染拡大の収束の兆しが見えない現在、在宅勤務は一時的なものではなく、多様で柔軟な勤務形態のひとつになりつつあります。
厚生労働省「改定テレワークガイドライン」によると、在宅勤務時の費用負担や通勤手当の取り扱いなど必要な事項については、あらかじめ労使双方で話し合い、状況に応じたルールを定め、就業規則などに規定することが望ましい、とされています。
検討事項の取り扱い方法によっては、社会保険等・源泉所得税に影響があるため、適切に対応する必要があります。
在宅勤務手当と社会保険等
在宅勤務手当は、企業が従業員に対し、在宅勤務に必要な費用を負担する名目で支給する手当です。
在宅勤務制度の導入にあたり、パソコンやネットワーク環境、備品などの初期費用や、光熱費や通信費などの維持費用の負担割合を検討する際に、費用補填として支給されます。
実務上、在宅勤務手当は、実費相当額を精算する方法(以下、「実費弁償」)にあたる場合を除き、社会保険料等の算定基礎の対象となります。
算定基礎となる「賃金、報酬及び賞与」とは、名称の如何を問わず、労働者が労働の対象として受け取るすべてのものを指します。
在宅勤務に必要な費用を従業員が立て替え、実費弁償を受ける場合は労働の対象と認められないため「賃金、報酬及び賞与」に該当せず、対象外となります。
通勤手当と社会保険等
通勤手当とは、従業員が通勤するために必要な費用を企業が負担するために支払う手当です。
通勤手当は、業務中の移動費用として支給する交通費とは異なり、実費精算などの支払い方法にかかわらず、社会保険料等の算定基礎の対象となります。
在宅勤務者が一時的に出勤する場合の通勤手当については、労働契約上の勤務地により取り扱いが異なります。
労働契約上の勤務地が「企業」である場合、通勤手当として、社会保険料等の算定基礎の対象となります。
一方、勤務地が「自宅」である場合は、業務中の移動費用として交通費の「実費弁償」にあたり、対象外となります。
源泉所得税の取り扱い
原則、企業が支給する手当は給与所得の一部と考えられるため、源泉所得税が発生します。
在宅勤務手当は、定額で支給され精算が不要な場合は、他の手当と同様、給与所得の一部として課税対象となります。
国税庁は「在宅勤務に係る費用負担に関するFAQ」により、給与課税の有無について合理的な算定方法を示しています。
在宅勤務において「実費弁償」となるものは非課税となりますが、通信費など業務のために使用した分は、算定方法に従って精算する必要があります。
通勤手当は、例外として所得税法により、交通手段別に非課税となる上限額があり、それを超えて支給されるものは給与所得の一部とみなされるため、課税対象となります。
実務上の対応ポイント
社会保険料の算定基礎については、新たに在宅勤務手当を毎月定額支給し、交通費を実費精算するなどにより、固定的賃金が変動する場合があります。
支給月以降の3カ月平均で2等級以上の変動があった場合は随時改定の対象となるため、月額変更届を忘れずに提出しましょう。
また通勤手当の実費精算については、就業規則などにおいて、通勤手当に関する記載の有無とその内容によっては不利益変更となる場合があるため、注意が必要です。
まずは就業規則などに、通勤手当の実費精算の方法あるいは返還や精算を求める記載があるかを確認し、必要に応じて追加修正を行い、従業員へ周知するなど適切に対応しましょう。