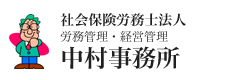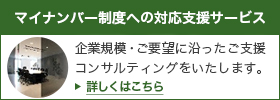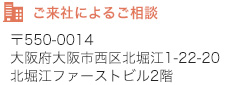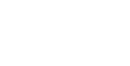育児休業中の就業の取り扱いはどうなるか 育児休業中の就業と育児休業給付金などへの影響
2022年10月にスタートした「出生時育児休業」を含む育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金や社会保険料の免除に対し、様々な影響が及びます。法改正に伴う育児休業の本質を踏まえて、その影響をお伝えします。
法改正の背景
育児休業とは、子の養育のため、労働者が法律に基づき取得できる休業です。労働政策審議会は、「少子高齢化社会においては、出産・育児による労働者の離職を防止し、男女ともに仕事と育児を両立できる職場環境の実現が重要である」としています。
育児・介護休業法は、2021年6月に男性の育児休業取得を推奨する方向で大幅に改正されました。
翌年4月1日より段階的に施行し、10月には、女性にとって心身の回復を最も必要とする出産直後の時期に、男性が育児休業を取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)がスタートしました。
育児休業期間中の就業
原則として、育児休業期間中は労務提供義務がないため、休業期間中に就業することは想定されていません。
ただし、あらかじめ労使協定を締結している場合に限り、一時的・臨時的に就業することができます。
あらかじめ決められた時間や日数、毎週特定の曜日や時間など、恒常的・定期的に終業させる場合は、育児休業をしていることにはならないので注意しましょう。
一方、出生時育児休業(産後パパ育休)においては、労使協定の締結を条件として、労働者が同意した範囲内で就業することが可能となります。
原則は就業不可のため、事業主が一方的に就業を命じることはできず、育児休業中に就業しなかったことを理由に、不利益な取り扱いをすることは禁じられています。
企業側は、育児休業給付金や社会保険料の免除に関する条件を説明した上で、労働者が就業の希望の有無を判断できるように対応することが大切です。
就業と休業給付金の調整
出生時育児休業を含む育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の休業給付金を受けることができます。
出生時育児休業給付金の支給には、就業日数に制限があるので注意が必要です。28日間(最大取得日数)休業した場合、就業日数は10日(10日を超える場合は80時間)、休業日数が28日より短い場合はそれに比例した日数(時間数)を超える場合は、休業給付金は支給されません。
また休業期間中に就業し賃金が支払われた場合は、これまで同様に調整が行われます。休業期間中に就業して得た賃金が、1. 休業開始時賃金月額の13%以下(181目以降は30%)である場合は全額支給、2. 13%(181目以降は30%)を超えて80%未満である場合は、休業開始時賃金日額に休業日数を乗じた額の80%から賃金額を差し引いた額を支給、3. 80%以上の場合は、休業給付金は支給されません。
出生時育児休業期間中に支払われた賃金額については、休業開始時賃金日額を基準とします。
就業と社会保険料の免除
3歳に満たない子を養育するための育児休業等期間については、事業主からの申し出により、各月の給与や賞与にかかる健康保険と厚生年金保険の保険料が被保険者負担分と事業主負担分ともに免除されます。
従来の免除要件は、「その月の末日が育児休業中であること」であり、育児休業開始日と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象とはならず、課題が残されていました。
法改正では、短期間の育児休業にも柔軟に対応できるようにするため、新たに「同一月内で14日以上の育児休業等を取得した場合」も免除要件に追加されました。
また賞与にかかる社会保険料に関しても、当該賞与月の末日を含み連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除対象となっています。
ただし、出生時育児休業を含む育児休業期間中に就業した場合は、免除要件である「14日以上」の日数に就業した日数は含まれません。